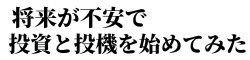「投資ブームっていうけど本当?」と周りの人を眺めて思っていませんか。
「隣のあの人も実は投資を始めていた…」という話は決して珍しいものではありません。
涼しい顔をして多くの人が投資を開始しているという話は、統計上正しいです。
正式な統計とともに、投資人口の増加について見ていきましょう。
Contents
2021年は金融資産が平均額ベースで増加
今回使用した資料は、金融広報中央委員会「知るぽると」の「家計の金融行動に関する世論調査2021年」です。
金融資産の保有額を2020年と2021年で比較すると、平均額は上昇しています。
一方で中央値は2020年と比べて約200万円減少しています。
<金融資産の保有額>
| 2020年 | 2021年 | |
| 平均額(万円) | 1,436 | 1,563 |
| 中央値(万円) | 650 | 450 |
この数字だけ見てみると、資産を増やした人と減らした人に二極化しているようです。
ひん。こわい。
金融資産の内訳を確認すると、どうやって資産を増やしたのか見えてきます。
資産増加した理由は有価証券等の価格上昇
各資産ごとに20年と21年で比較してみましょう。
グラフを見てみると、預貯金に大幅な変化はありません。
一方で、有価証券は大幅に増えていることが分かります。
ここで気になるのが、保険の減少です。
ここ数年のトレンド?で保険不要論が広がりつつあるのを肌で感じますが、その影響でしょうか。
もしかしたら、保険を解約して有価証券へまわした人もいるのかもしれませんね。
このグラフから言えることは、預貯金のみの人は20年から21年にかけて資産が微減しているので、預貯金のみだと資産を減らしている人もいる可能性があります。
有価証券の保有額が上昇しているということは、以下の2つの要因が考えられます。
- 新たに有価証券を購入した
- 以前から保有していた有価証券が上昇した
投資ブームに乗じて有価証券等を購入した人は少なくないでしょう。
また、何年も前から有価証券を保有している人やコロナショック時に有価証券を購入した人は、今のところ含み益の人が多いと考えられます。
実際にアンケートでも金融資産が増えた理由のトップが「株式、債券価格の上昇により、これらの評価額が増加したから」でした。
資産が減った理由は収入の減少
資産が減った人の1番の理由は「定例的な収入が減ったので金融資産を取り崩したから」です。
51.8%の人が収入の減少を理由としています。
具体的な理由について明記されていないものの、コロナの影響によるものでしょう。
コロナの影響を受ける職種に就き、金融資産が預貯金のみだった場合、資産額は減少していてもおかしくありません。
投資に対するスタンスが1年で大きく変化
有価証券等の評価額が急上昇したせいか、投資に対するスタンスが20年と21年で大きく変化しています。
金融商品を選ぶときに重視すべきポイントを項目ごとに比較してみると一目瞭然です。
なんと、安全性を求める人の割合が減少して収益性を求めている人が増加しています。
「投資はギャンブルだ」なんて言われていた時代は、この数年で一気に過ぎ去ったのかもしれません。
元本割れリスクのある金融商品に対する考え方をグラフで見ていきましょう。
「保有したくない」と考えている人の割合が1年で逆転しています。
また、積極的に保有したいと考えている人の割合が大幅に上昇しているのも面白いですね。
数値で確認すると、このように変化しています。
- 20年 4.40% → 21年 14.50%
3倍以上ってすごくないですか??
やはり、コロナショック以降の爆上げでウハウハだったり、その様子を見たりして強気なマインドになっている人が多いのかもしれません。
総じて、投資に対するネガティブイメージは払拭されつつあり、むしろ積極的に保有していきたいと考えている人が増加しているようです。
老後の心配はあるものの強気な姿勢の割合も増加
老後の生活についての回答も興味深かったです。
直近の株高が老後の生活イメージを変えている可能性があります。
老後の生活に関する質問で、基本的に老後の生活について不安を抱えている人は多いものの、楽観的に考えている人の割合も微増しているので確認しましょう。
<老後の生活の心配>
| 非常に心配だ | 多少心配だ | それほど 心配していない | |
| 2020年 | 35.7% | 42.3% | 20.7% |
| 2021年 | 35.2 % | 41.8% | 23.0% |
ただし、この表だけだと「心配していない」の数値で投資に対して強気な姿勢が老後の生活まで波及しているとは判断できません。
老後の生活をどのような収入でまかなうつもりなのか見ていきましょう。
利子や配当所得で老後を送る割合の増加
どのような収入で老後の生活をまかなうつもりなのか?という設問をグラフ化しました。
この設問は3つまでの複数回答可です。
変化が面白かったので2019年も含めてグラフ化しています。
2019年と2020年はそこまで割合に大きな変化はみられません。
強いていうなら、子からの援助が減っているくらいでしょうか。
しかし、2020年から2021年を比べてみると、利子配当を収入源として考えている人の割合が一気に増加しています。
また、公的年金をあてにしている人の割合が減っているのも面白いですね。
そして、2021年も子からの援助は減り続けています。
まぁ、若い世代は生きていくだけでヒィヒィ言ってますからね…子世代をアテにしないで老後は過ごしてもらいたいものです。
老後の収入源についての表を見る限り、投資に対して「長く付き合う」というスタンスの人が増えていると考えられます。
2020のコロナショックから株価は爆上がり
この1年でなぜここまで世間が投資に対して強気なのかというと、コロナバブルがあったからです。
また、FIREという言葉もここ数年で一気に市民権を得ました。
順調な株価の上昇と、FIREして仕事から縛られない生き方という新たな価値観が出てきたことが少なからず影響していると思っています。
実際に日経チャートとダウチャートを見ていきましょう。
日経チャート
日経平均株価の5年チャートです。
日本の株価は米国株と比べてパッとしないと言われているものの、2020年のコロナショック以降は急激に株価を回復させています。
コロナショック時に株を購入しようと動いた人はそれなりにいた(実際に見かけた)ので、現在は含み益でウハウハでしょう。
また、コロナショック以前と比較しても上昇していることから、2020年以前から株を保有しているケースでもウハウハな人が多いです。
ダウチャート
ダウの5年間チャートを見ていきましょう。
2020年で一気に急降下していますが、鬼のように急上昇しているのが分かります。
米国のチャートもコロナショックで一時的に株価急落しましたが、現在は回復してむしろ以前よりも高値で推移しているのです。
日本株と同様に、コロナ以前から保有していた人やコロナショックで買い向かった人はウハウハでございます。
今は高値更新していないので落ち着いているものの、21年にかけてぐんぐん株価が上昇していた時期はおそらくみなさん熱狂していたことでしょう。
投資に対する考え方やスタンスを大きく変えた要因のひとつが株価の上昇だと思っています。
投資家が爆増は事実|今後の爆益は不透明
日本で投資を行っている人が爆増しているのは事実です。
現に、つみたてNISAやNISAの口座開設数は増加傾向にあります。
<つみたてNISA・NISAの口座開設数>
| つみたてNISA | NISA | |
| 2020年末 | 172万口座 | 742万口座 |
| 2021年末 | 339万口座 | 769万口座 |
若い世代で口座開設数が増えているため、将来の不安を投資で解消しようとしている側面は否めないものの、株価の上昇が寄与しているところはあるでしょう。
20~30歳代の口座開設数は20年と21年で約100万件増えており、21年末で300万口座に到達しています。
おそらく、職場や電車で毎日顔を合わせているあの人もこの人も、きっと投資を始めていることでしょう笑。
今後の株価の上昇は不明
当たり前のことですが、今後直近で株価が上昇するか否かは誰にも分かりません。
ただし、人口が増え続けてイノベーションが起き続ける限り経済は発展していきます。
経済が発展すれば必然的に株価も上昇するため、20、30年スパンで見れば株価は上昇していく可能性が高いです。
ただし、元本割れする可能性も同様にはらんでいますけどね。
ただ、世界経済の発展を期待するなら、オルカンはリスクとリターンのバランスが良いので長期で取り組む投資に向いていると思います。
また、ニュースでも1億総株主と国民に投資を促す方向で政治が動いています。
もしかしたら、「投資をしない」という選択肢はなくなっていくのかもしれませんね。