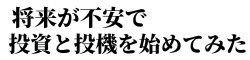「年金は運用しているから心配ない」や「本当に年金もらえるのかよ」とネットや会話で見聞きするものの、実際はどのようになっているのか分からない人は多いと思います。
現役世代から徴収しているお金で余った分は年金積立金として、GPIFという機関が投資しています。
GPIFは安定的な長期投資により、莫大なインカムゲインと含み益を達成している最強の投資手腕をもっている機関です。
今回は最強の投資機関とも言えるGPIFについて紹介します。自身の資産形成について、本当に年金をアテにしていいのかも私見を述べているので参考にしてください。
Contents
GPIFとは
GPIF(Goverment Pension Investment Found)は金積立金の管理・運用を行って、年金財政を安定させるための組織です。運用によって得られた収益を国庫に納付しています。
GPIFの投資原則は、我々庶民の老後資金構築するときに通ずるものがあるので確認しましょう。
- 年金財政上必要な利回りを最低限のリスクで確保
- 長期投資で安定的で効率良く収益を確保
- パッシブ(受け身)運用とアクティブ(活動的)運用の併用
GPIFは長期的な運用でリスクを極力回避して安定的な収益を目指しており、現に莫大なリターンを得ています。
年金積立金の運用とは
そもそも年金積立金とは、国民が納めた保険料のうち、年金給付に使われず余ったお金を積み立てたものです。この積立金は将来の年金給付に使われます。
年金積立金の運用とは、将来の現役世代の負担が重くなりすぎないように、年金積立金を運用していくことです。運用収入を得て、将来の年金給付のための財政運営を行っています。
運用収入とは国内外の債券や株式等を組み合わせた分散投資によるものです。
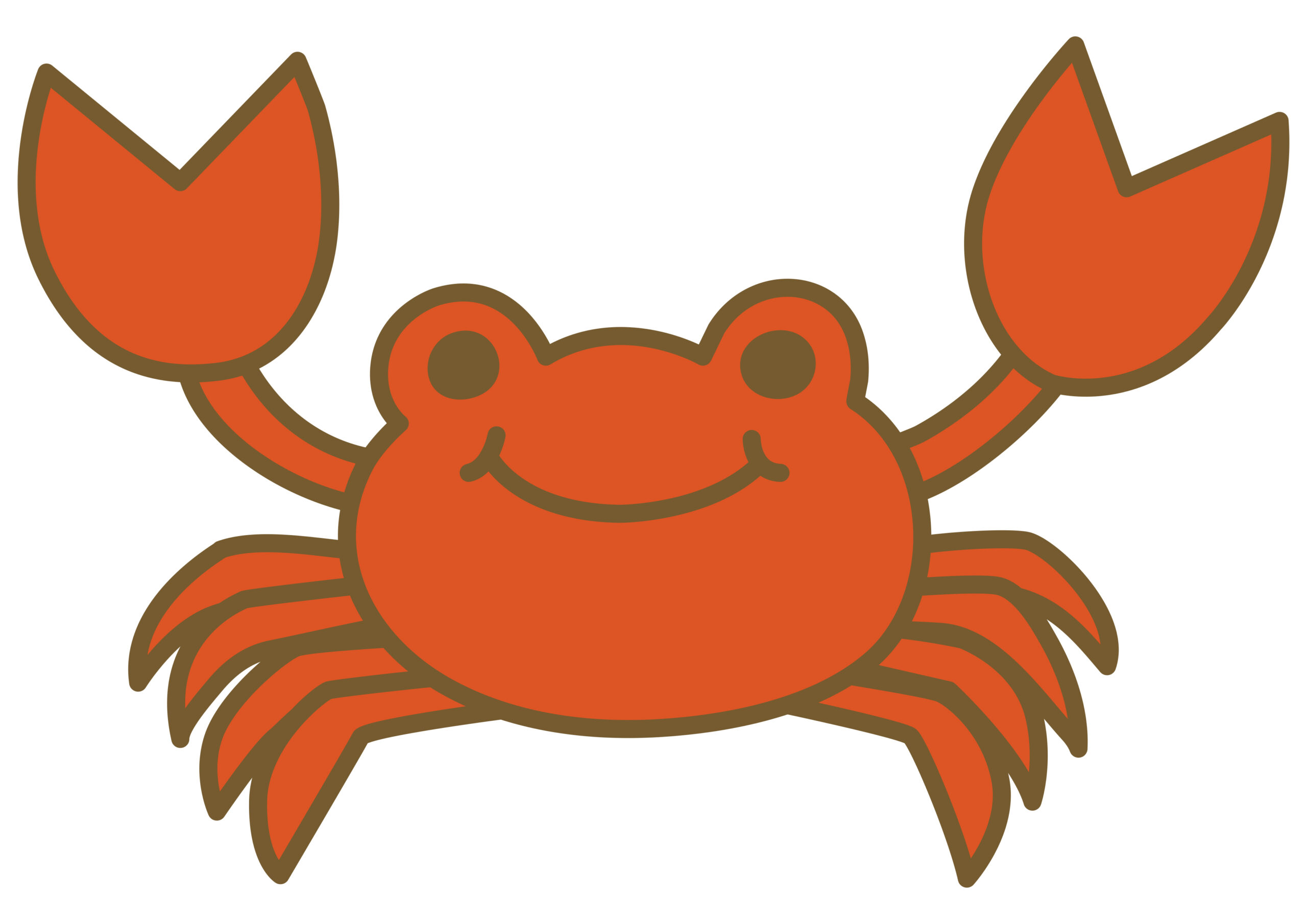
実際に資産を運用するときは、自家運用している国内債券等の一部を除いて、民間の信託銀行や投資運用会社を利用しているよ!
このような我々の年金積立金を運用している機関が、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)です。GPIFは年金給付する予定の一部を、将来の世代のために運用して増やしています。
GPIFの運用成績は長期投資による安心安全で最強
GPIFの運用成績は長期投資を前提としているため、元本割れの年があったとしてもトータルで見るとプラスの成績を叩きだしています。
一般的に長期投資は資産形成に適していると言われているものの、含み益になるとつい売却してしまう人は多いのではないでしょうか?
GPIFの運用成績や累積収益額など詳しく見ていきましょう。
GPIFが身体を張って長期投資運用を行って現に3%以上の含み益を確保しているため、我々庶民の資産形成方法の参考になるはずです。
運用開始以降・2021年の運用成績
運用開始以降と2021年度、2022年第三四半期のGPIFの運用成績を確認しましょう。
| 2021年度 | 2022年第三四半期 | 運用開始以降 (2001年度~2022年度第3四半期) | |
|---|---|---|---|
| 収益率 | +5.42% (年率) | -0.97% (期間収益率) | +3.38% (年率) |
| 収益額 | +10兆925億円 (年間収益額) | -1兆8,530億円 (期間収益額) | +98兆1,036億円 (累積収益額) |
| 利子・配当収入 | 3兆1,983億円 | 1兆1,007億円 | 46兆4,116億円 |
2022年第三四半期の成績からもわかるように、市場で運用しているため、マイナス収支に陥る期間は避けられません。
しかし、20年以上の運用で収益率は3.38%と安定した成績を出しています。
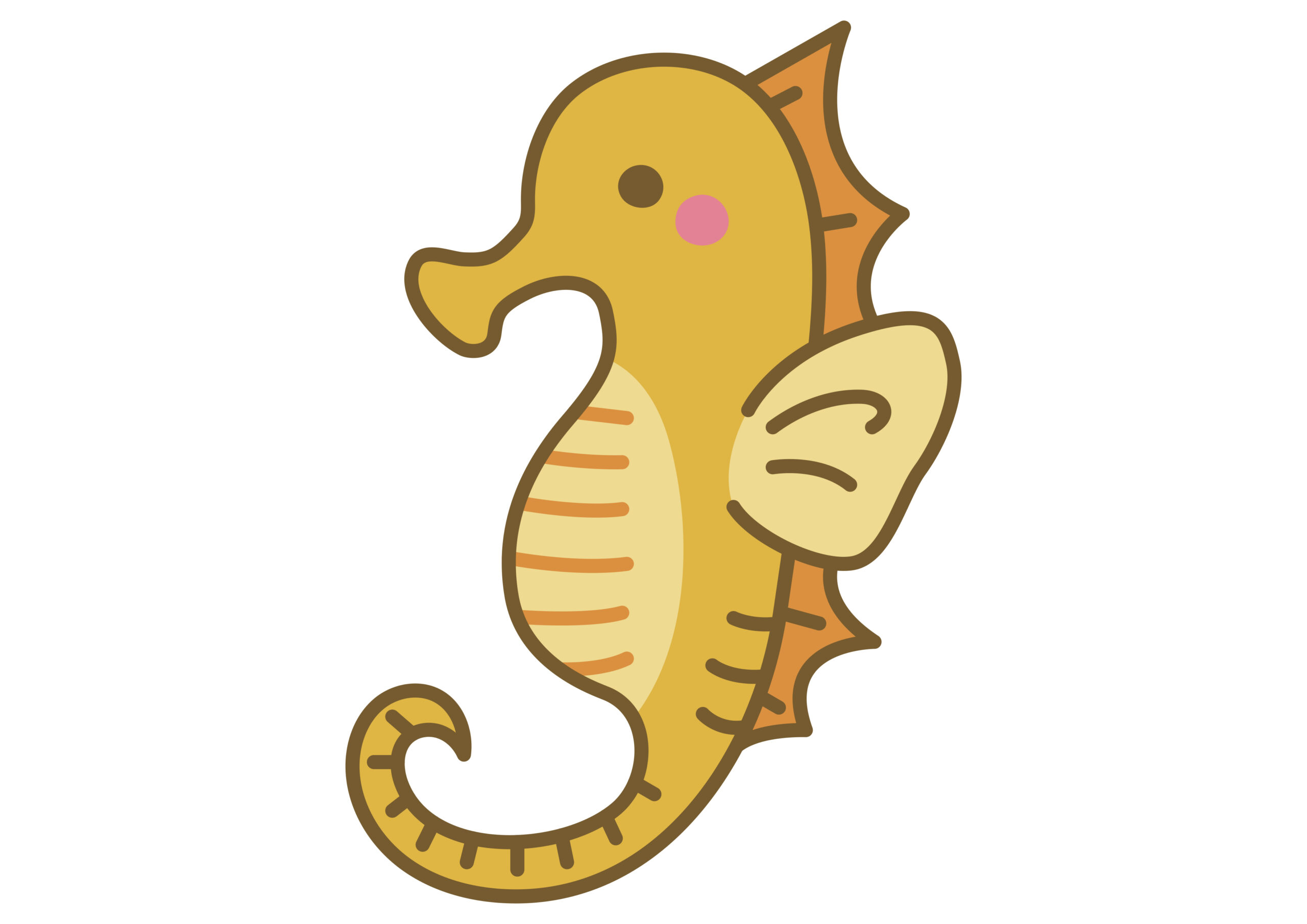
運用金額が莫大なため、利子・配当収入もかなりの額になっていますね…。
元手の大きさは資産運用において正義だとわかります。
GPIFから2022年度の運用成績が発表されました!
筆者のiDeCoは2022年度はマイナスの利回りだったのですが、守りのGPIFはしっかりプラスの結果で着地しています。
| 収益率 | 1.5%(年率) |
| 収益額 | 2兆9,536億円(年間) |
| 収益額 (インカムゲイン) | 3兆7,003億円(年間) |
長期運用による収益とインカムゲイン
GPIFの長期運用による累計収益とインカムゲインの経過をグラフで確認しましょう。
参考:GPIF 2021年度業務概況書 をもとに作成
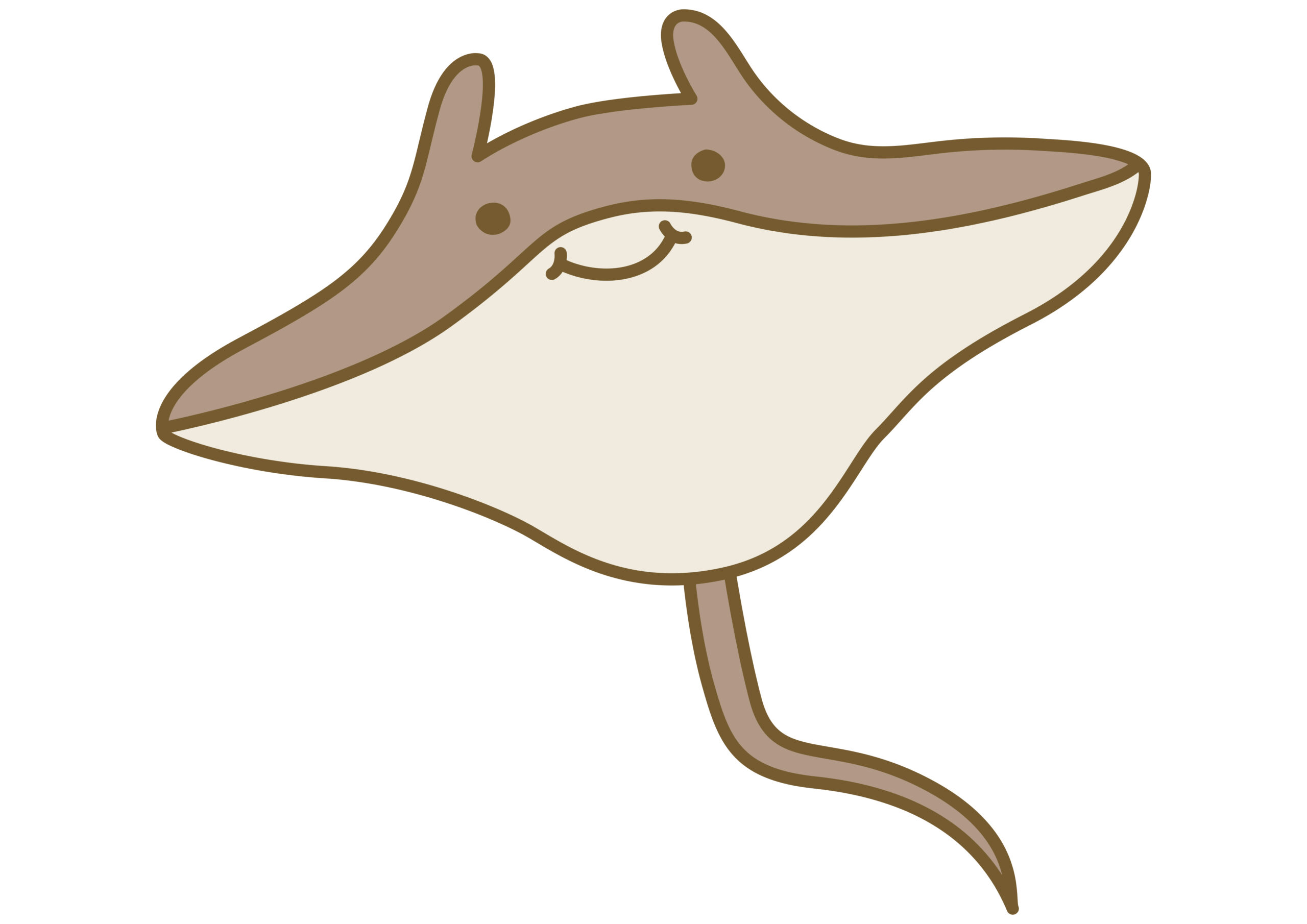
市場運用を開始した2001年は最悪の景気だったと言われているよ
日本経済は、2000年10月に景気の山を越え、景気後退局面に入った。 その後、2001年を通じて、生産は大幅に減少するとともに、失業率も既往最高水準を更新し、景気は悪化を続けた。 実質経済成長率は、2001年4-6月期以降マイナスに転じた。
そのため、2001・2002年はマイナス収支になっています。
また、累計収益額が激減した2008年はリーマンショックが起きた年です。
市場で運用しているため、年度によって変動しているものの、20年以上運用し続けると徐々に累計収益額が積みあがっていることがわかります。
そして、利子・配当の安定した強さよ…
GPIFのポートフォリオ
安定した投資成績を出しているGPIFのポートフォリオは誰しもが気になると思います。
GPIFは5年計画で運用利回り(運用利回りから名目賃金上昇率を差し引いたもの)1.7%を確保することを目標に、基本となるポートフォリオを作成しています。
基本・2022年の実施ポートフォリオは、以下の表の割合です。
| 国内債券 | 海外債権 | 国内株式 | 海外株式 | |
|---|---|---|---|---|
| 基本構成割合 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 乖離許容範囲 | ±7% | ±6% | ±8% | ±7% |
| 2022年度 構成割合 | 26.79% | 24.39% | 24.49% | 24.32% |
GPIFの具体的な投資先は不明ですが、基本ポートフォリオをもとに国内外の債券と株式をほぼ等しい割合で運用しています。
以前は国内債券35%・海外債券15%の割合で運用していましたが、現在、国内の金利低下により国内債券の利回りが低下しています。そのため、相対的に金利が高い外国債券の割合を増やして調整しているようです。
具体的な投資内容が知りたい!
国内・海外株式で運用するときに、具体的にどこの会社に投資しているのか知りたいのが庶民の本音。
さすがに具体的な投資先は明記していないものの、ホームページ上では以下のように書かれていました。
GPIFは国内外の1万銘柄以上の債券と、約5000社の株式に分散投資することで、長期的に見て効率的で安定した運用を目指しています。
やはり成長ジャンル・企業に集中して投資するよりも、様々な企業に投資した方が安定的なリターンを得られるようです。
GPIFの運用を参考にすると、一般市民が株式投資するなら国内外の企業に幅広く投資できるオールカントリーが良いという結論に至りますね。
GPIFは株主優待をどう処理しているの?
ここで気になるのが、株主優待の扱いです。国内企業だと配当のほかに株主優待として割引券や現物支給されることがありますが、どのように使われているのでしょうか。
株主優待の割引券などはできる限り現金化して、収益の向上に寄与しているようです。2021年度実績だと、運用収益のうち約3億円が換金されたものです。
また、食品・家庭用品などの現物は日本赤十字社や東京都福祉協議会などに寄付しており、福祉にも役立つ仕組み作りがなされています。
GPIFの分散投資の考え方
安心安全かつ目標運用利回りを達成させるGPIFの分散投資の考え方を見ていきましょう。
- 1番儲かる投資ではなく損をしない投資
- 債券と株式は相関関係が低いため安定投資が可能
庶民の資産形成に役立つはずです。
1番儲かる投資ではなく損をしない投資
GPIFは最も儲かる投資法ではなく、損をしないための投資を行っています。
毎年、資産を大きく伸ばせるジャンルを当て続けることは無理と言っても過言ではありません。そのため、GPIFでは以下の主要4資産に分散して投資しています。
- 国内債券
- 国内株式
- 外国債券
- 外国株式
4資産に分散して運用を行えば、仮に外国株式が暴落したとしても国内債券がプラス収益になるため、大きな損失を免れることが可能です。
債券と株式は相関関係が低いため安定投資が可能
債券と株式の組み合わせだと値の動き方が異なる(相関関係が低い)ため、片方が暴落しても、もう一方から安定した収益を得られる可能性が高いです。
相関関係の低い資産を組み合わせて投資すると、リターンは各資産の平均になると言われています。一方で、リスクは平均より小さくすることが可能です。
つまり、1つのジャンルに集中投資する場合に比べ、分散させてリスクを小さく抑えたほうがリターンを安定でさせられます。
特に、債券と株式は値の動き方が異なる性質を持つため、分散投資に効果的です。また、国内と国外それぞれに投資すれば、より安定的な運用ができます。
5年に1度厚労省による財政検証が行われる
年金の積み立て状況は、5年ごとに厚労省による財政検証により見直しされています。
下記の人口学的要素と経済学的要素の前提により、今後100年間にわたる収支状況を推計し、財政見通しを算出しています。
- 将来の加入(若年人口)
- 脱退・死亡・障害等
- 運用利回り
- 賃金上昇
- 物価上昇の状況
参考:給付水準の将来見通し
GPIFは上記の数値をもとに目標運用利回りを設定しています。
現在の運用目標利回りは1.7%のところ、各年度までの累積の年率換算値で3.78%の利回りです。
年金に関し、安定的な財政運営ができていると言えます。今のところ「年金が大幅に足りない!」という状況になることはないでしょう。
年金積立金での検証での推計は安心できない
定期的に財政健全性を検証しているとはいえ、安心できる要素ばかりではありません。
個人的に財政検証の推計は少し甘い気がします。
なぜなら、出生中位 1.44で計算していますが2023年時点で出生率は1.26にまで落ち込んでいるからです。若年人口が増えなければ労働人口も増えないため、経済成長に影響が出る可能性があります。
そのため、推計と実態に乖離が出てきてもおかしくありません。
ただし、今のところ運用目標利回りを超えて収益を得られているため、悲観しすぎる必要はないでしょう。
GPIFの堅牢長期投資を見習って老後資産を構築しよう
我々が毎月徴収されている年金保険料は、余剰金を運用して安定的な利回りを出しています。
GPIF・社会保障費問題について知識を得ると、「年金をもらえなくなるのは嘘だけど、年金の心配を全くする必要がないというのも眉唾」だと感じた人が多いのではないでしょうか。
新NISAが始まることですし、年金給付に頼り切りにするのではなく、GPIFの堅牢長期投資を見習って自分で資産を構築した方が安心できます。
会社が確定拠出型年金(iDeCo)を推進しているならiDeCoでも積立てましょう。その場合、株式と債権を組み合わせると、飛躍的な含み益は期待できないものの安定的に運用できます。
新NISAは積立てたら解約せずに老後までグリップするつもりで投資することが大切です。
GPIFの堅牢な長期投資を見習って老後資産を構築しましょう。