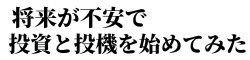高卒女子でも就職自体は余裕でできます!
しかし、職種や企業を選ばないと、のちのち賃金格差や子育ての両立の難しさに悩むことになるでしょう。
なぜなら、高卒女子の賃金上昇カーブは非常に緩やかだからです。また、福利厚生が手厚い企業に就職できる人は決して多くないため、産後復帰しづらい企業に当たるかもしれません。
高卒女子の就職事情と自己都合退職の多い職種を確認して、長く会社員生活を送るためのコツを紹介します。
Contents
高卒女子でも就職はできる
令和4年3月高等学校卒業者の就職状況を見てみると高卒女子の就職率は97.0%です。ほぼ全員が就職できる状況だと言ってもよいでしょう。
そのため、「高卒だけどちゃんと就職できるかな?」と心配する必要はありません。業種や会社を選ばなければ就職先は見つかります。
早く自立したい高卒女子にとって、高校からの就職でもほぼ全員が仕事を見つけられるという事実は大きな安心材料になるはずです。
問題は給与や休日日数、福利厚生などQOLを左右するポイントが充実している職種が少ないことです。
高卒女子の年収は低いことを覚悟して
高卒女子でもほぼ全員が就職先を見つけられますが、長期的に考えると年収が低くなりがちなことを覚悟しなくてはなりません。
高卒女子の年収は同じ高卒男性よりも低いです。また、専門卒や大卒女性よりも年収は低くなります。
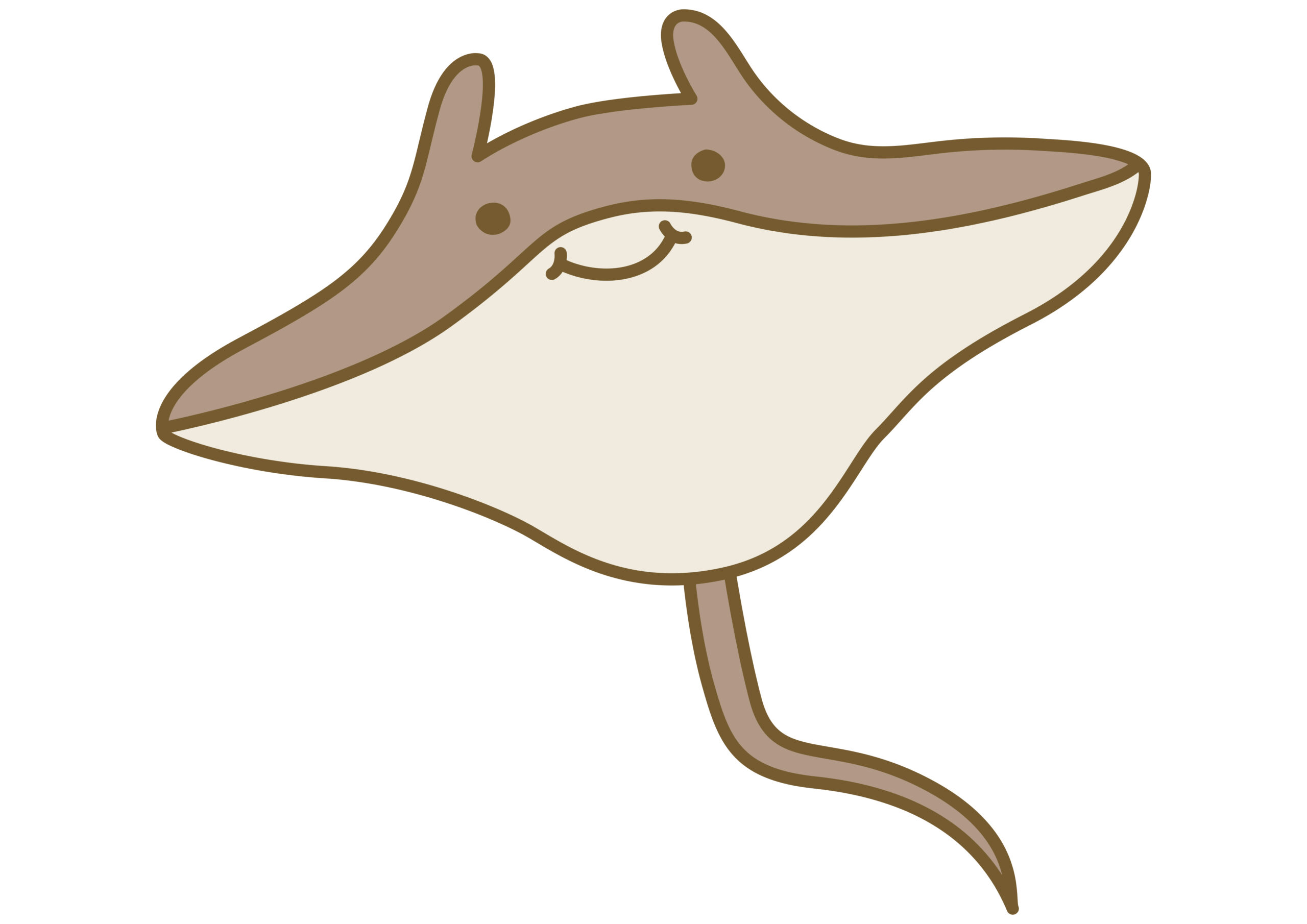
高卒で就職すれば10代のうちからまとまったお金を手に入れられますが、生涯賃金ベースで考えるとどうしても少なくなってしまいます。
どのくらいの差がでるのか、以下の項目で確認しましょう。
- 同じ高卒で男女別の年収差
- 女性で学歴別の年収差
高卒女子で就職したときの解像度を上げましょう。
高卒|男女別の年収の違い
同じ高卒でも男女で年収の違いがでます。
厚生労働省より、令和3年度の賃金調査が発表されているので、以下の表で確認しましょう。
ここでいう賃金とは、各種手当を差引いた額で所得税などが控除される前の金額です。額面ベースの基本給だと考えてください。
| 性別 | 年齢 | 月給(円) | 年収(円) | 性別 | 年齢 | 月給(円) | 年収(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | ~19 | 185,600 | 2,969,600 | 女性 | ~19 | 177,000 | 2,832,000 |
| 20~24 | 204,300 | 3,268,800 | 20~24 | 190,000 | 3,040,000 | ||
| 25~29 | 234,500 | 3,752,000 | 25~29 | 202,000 | 3,232,000 | ||
| 30~34 | 261,100 | 4,177,600 | 30~34 | 212,000 | 3,392,000 | ||
| 35~39 | 284,700 | 4,555,200 | 35~39 | 216,000 | 3,456,000 | ||
| 40~44 | 307,700 | 4,923,200 | 40~44 | 222,300 | 3,556,800 | ||
| 45~49 | 332,700 | 5,323,200 | 45~49 | 234,700 | 3,755,200 | ||
| 50~54 | 346,500 | 5,544,000 | 50~54 | 236,500 | 3,784,000 | ||
| 55~59 | 351,800 | 5,628,800 | 55~59 | 240,000 | 3,840,000 | ||
| 60~64 | 271,400 | 4,342,400 | 60~64 | 208,900 | 3,342,400 | ||
| 65~69 | 230,000 | 3,680,000 | 65~69 | 200,000 | 3,200,000 | ||
| 70~ | 222,600 | 3,561,600 | 70~ | 202,900 | 3,246,400 |
年収はボーナス年間4ヵ月分として、月給×16ヵ月で計算しています。企業によってボーナスの計算は異なるため、あくまでも参考程度にしてください。
女性は400万円を超えずに下降カーブに突入していきます。一方男性は、550万を超えます。同じ学歴でもここまで差がでるのは辛いですね…。
視覚でわかりやすいように男女別の月給をグラフにしました。
年齢を重ねるごとに賃金の差が大きくなっています。
学歴は一緒でも男女の賃金格差が発生する原因は2つです。
- 男性は現場仕事で稼いでいる可能性が高い
- 結婚・妊娠・出産・育児により賃金の上昇を抑えられている
人手不足の現在、事務仕事よりも現場仕事の方が賃金上昇率は高いです。事務職は全世代の女性から人気のある職種のため、派遣やパートでやりくりしているケースは少なくありません。
また、女性は妊娠・出産・育児などが絡んできます。育休後復帰したとしても、時短勤務や昇進の遅れなどで、どうしても賃金カーブはなだらかになりがちです。
女性|学歴別の年収の違い
学歴別での賃金格差は大きなものです。女性の高卒と大卒での年収の違いを表にまとめました。
| 最終学歴 | 年齢 | 月給(円) | 年収(円) | 最終学歴 | 年齢 | 月給(円) | 年収(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高卒 | ~19 | 177,000 | 2,832,000 | 大卒 | ~19 | 0 | 0 |
| 20~24 | 190,000 | 3,040,000 | 20~24 | 227,500 | 3,640,000 | ||
| 25~29 | 202,000 | 3,232,000 | 25~29 | 252,300 | 4,036,800 | ||
| 30~34 | 212,000 | 3,392,000 | 30~34 | 275,500 | 4,408,000 | ||
| 35~39 | 216,000 | 3,456,000 | 35~39 | 298,200 | 4,771,200 | ||
| 40~44 | 222,300 | 3,556,800 | 40~44 | 323,300 | 5,172,800 | ||
| 45~49 | 234,700 | 3,755,200 | 45~49 | 335,200 | 5,363,200 | ||
| 50~54 | 236,500 | 3,784,000 | 50~54 | 383,000 | 6,128,000 | ||
| 55~59 | 240,000 | 3,840,000 | 55~59 | 371,100 | 5,937,600 | ||
| 60~64 | 208,900 | 3,342,400 | 60~64 | 311,600 | 4,985,600 | ||
| 65~69 | 200,000 | 3,200,000 | 65~69 | 374,600 | 5,993,600 | ||
| 70~ | 202,900 | 3,246,400 | 70~ | 389,900 | 6,238,400 |
年収はボーナス年間4ヵ月分として、月給×16ヵ月で計算しています。企業によってボーナスの算入期間は異なるため参考程度にしてください。
新卒の20~24才時点で大卒者の方が高額な賃金を得ています。
高卒女子は早くから収入を得られるとはいえ、35~39才時点でこれまで稼いできたトータルの収入は追い付かれてしまいます。大卒であれば、女性でも年収600万は夢ではありません。
学歴別の月給をグラフで確認しましょう。
高卒女子の月給の上昇率はなだらかですが、大卒だと50代にかけてグッと伸びてきます。おそらく、役職に就く女性の賃金によって数値が引き上げられているのでしょう。
大卒者だと定年後の再雇用でも良い条件で働けています。一方、高卒者は年齢を重ねてもほぼ賃金上昇しておらず、むしろ60才を過ぎると月給が一気に下がります。
老後に金銭的な苦労をせずに過ごすなら、大卒で働き続ける方がよいでしょう。
高卒女子は正社員を続けるハードルが高い
高卒女子は大卒女子と比べて正社員を続けるハードルが高いです。
少し古い資料ですが、【序章 「日本的高卒就職システム」の現在 第1章 マクロ統計にみる新規高卒労働市場の変化より、2017年の女性全体での非正規雇用者の割合は15~24才で約35%、25~34才で約40%です。
女性非正規雇用の割合を学歴別に分けたときの割合を以下の表にまとめました。
| 年齢 | 中学・高校卒 | 大卒・大学院卒 |
|---|---|---|
| 15~24才 | 40%強 | 20%弱 |
| 25~34才 | 60%弱 | 20%強 |
中学・高卒者だと、いわゆる結婚・出産適齢期25~34才のときに正規雇用から外れて非正規雇用になる割合が大きいです。
一方で、大卒・院卒者は結婚・出産適齢期でも非正規の割合に大きな変化はありません。
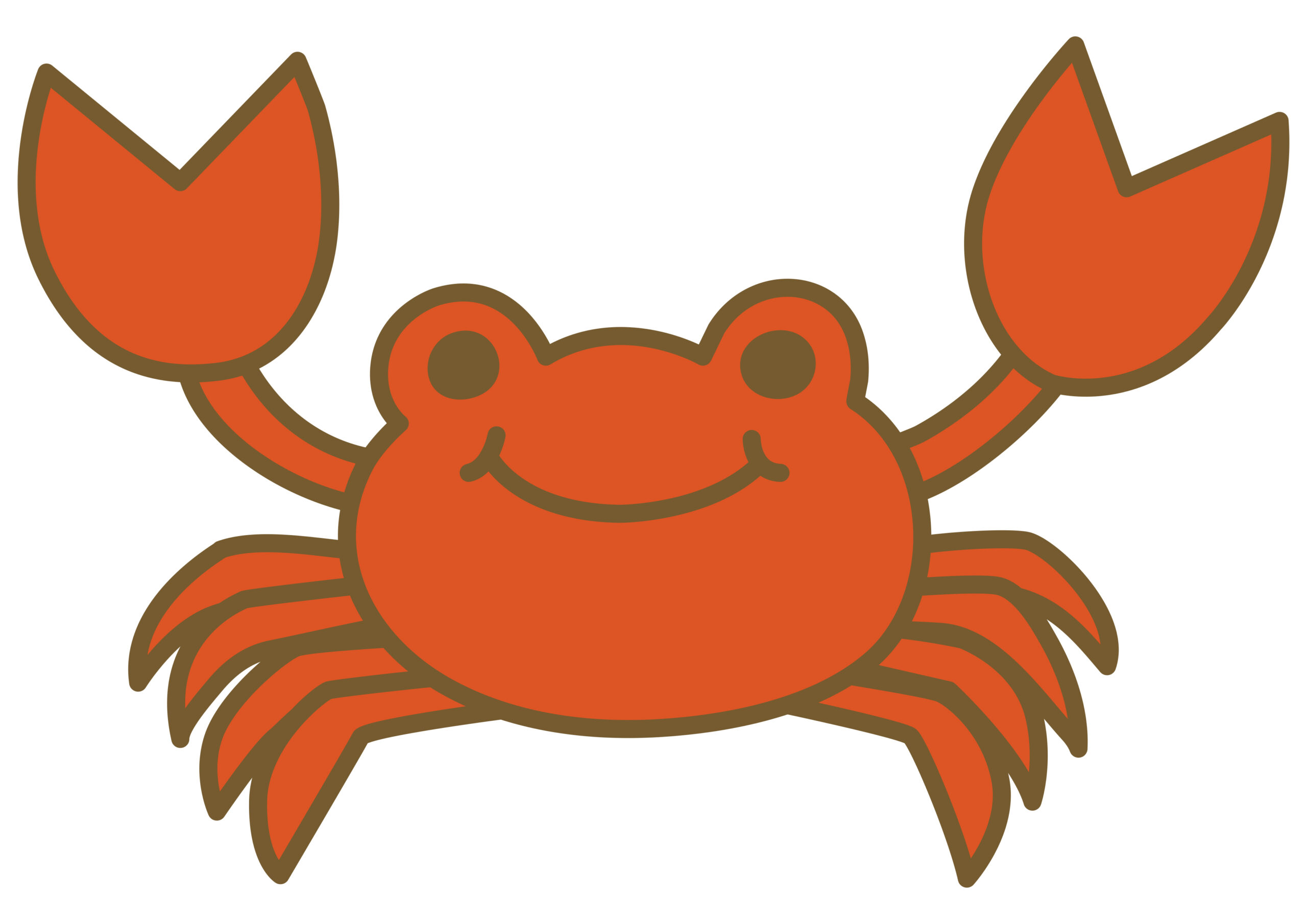
中卒・高卒者で妊娠・出産すると産休から戻ってこれない雰囲気や復職するメリットを見いだせないといった労働環境があるのだろうと推測できます。
たとえば、人手の足りない職場の場合、つわりで体調が悪くても休めなかったり保育園からの呼び出しに良い顔をされないケースがあります。
長く勤めたくてもフォロー環境が整っておらず、辞めざる得ない状況は令和の時代でも少なくありません。
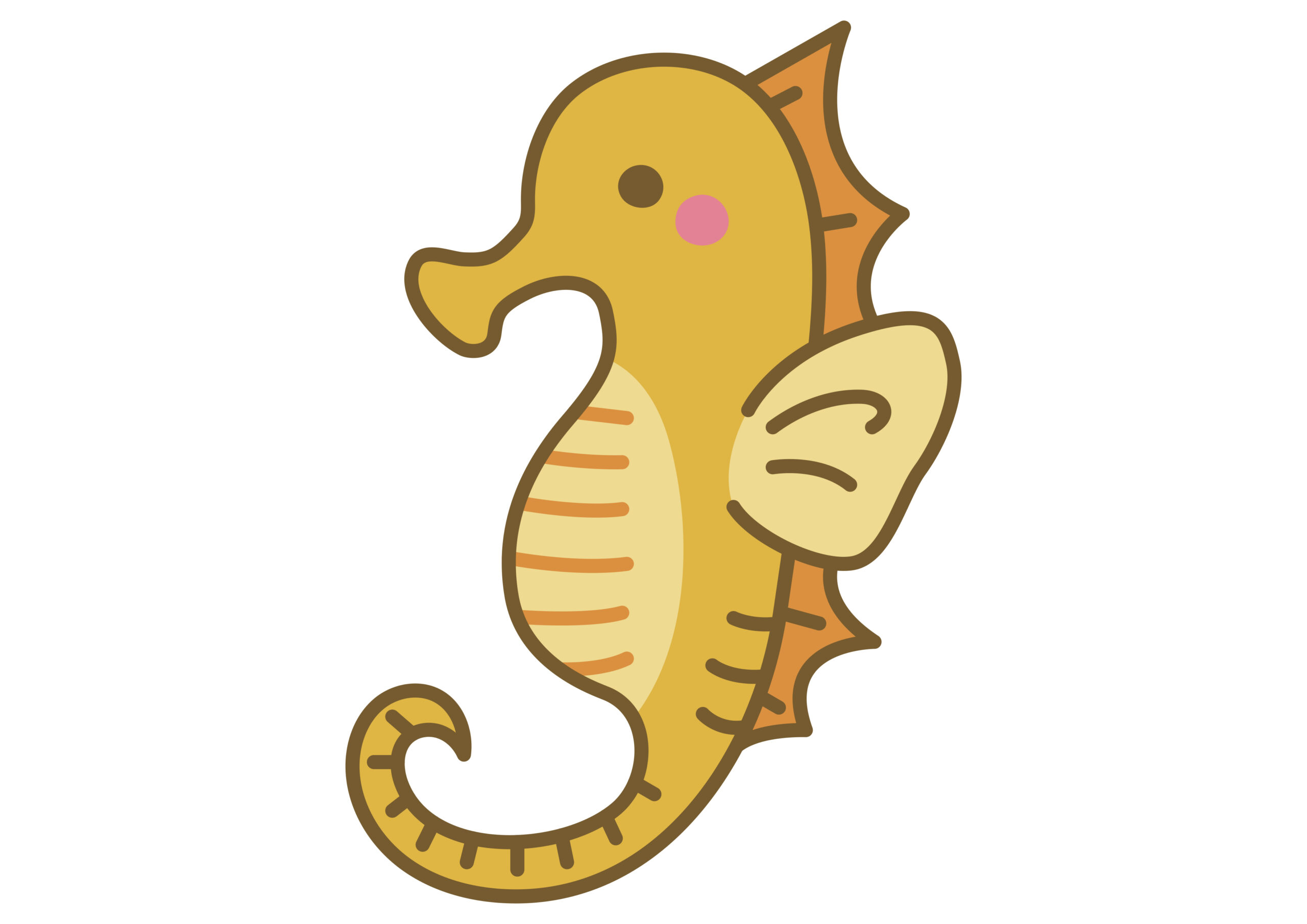
一度正規雇用から外れると、非正規雇用から抜け出せない日本の状況を考えると、なかなか厳しいものがありますね。
高卒女子をとりまく就職状況
高卒女子の就職率は高く、就活をしっかり行えばちゃんと就職できます。ただ、働く業界を知らずに就職すると、早い段階で非正規雇用になってしまう可能性があります。
高卒女子をとりまく就職状況について以下の項目で確認しましょう。
- 高卒新卒者の業界ごとの求人状況
- 自己都合退職の多い職種とは?
- 小規模企業の求人が多い
業界ごとの求人状況や自己都合退職しやすい職業を把握して、長く働ける環境を選びましょう。
高卒新卒者の業界ごとの求人状況
高卒で就職活動すると、どのような業界に就職できるのか確認しましょう。
高校新卒者のハローワーク求人に係る産業別求人状況を表にまとめました。
| 産業分類 | 令和4年(人) |
|---|---|
| 製造業 | 133,790 |
| 建設業 | 73,602 |
| 卸売業,小売業 | 45,394 |
| 医療,福祉 | 38,602 |
| 運輸業,郵便業 | 26,875 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 24,114 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 17,870 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 15,376 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 7,175 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 4,393 |
| 複合サービス事業 | 3,683 |
| 情報通信業 | 2,804 |
| 農・林・漁業 | 2,659 |
| 金融業,保険業 | 2,031 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,021 |
| 教育,学習支援業 | 509 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 399 |
| 公務,その他 | 97 |
| 合計 | 401,394(人) |
ハローワーク経由だと製造業と建設業といった、いわゆるブルーカラーと言われる業界からの求人が多いです。製造業や建設業に女性が就職するとなると事務職が考えられますが、少数でしょう。
高卒女子の求人が多い業界として、以下の職種が考えられます。
- 卸売業,小売業
- 医療,福祉
- 宿泊業,飲食サービス業
就職先として、対人サービスを提供する業界からの求人が多いと推測できます。
自己都合退職の多い職種とは?
自己都合退職について詳しく見ていきましょう。産休育休、年金などのことを考えると自己都合退職の少ない、つまり長く勤められる業界・企業に就職することが大切です。
就職後3年以内離職率のうち、離職率の高い上位5産業を以下の表にまとめました。
| 産業 | 割合 |
|---|---|
| 宿泊業,飲食サービス業 | 61.1% |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 56.9% |
| 教育,学習支援業 | 50.1% |
| 小売業 | 47.8% |
| 医療,福祉 | 46.2% |
生活関連サービス業は美容室、エステティックサロンや旅行代理店などを指し、娯楽業は映画館や劇場などを指します。
土日祝日休みではない、週末や長期休暇に稼働する業界の離職率が高いです。就業時間が不規則な業界が多いことも読み取れます。また、対人サービスを提供する業界での離職率が高いことも特徴です。
しかし、自分が志望している業界が宿泊業や医療福祉業なら、その業界を第一志望にする就活をおすすめします。なぜなら、好きな業界ならやりがいを持って長く続けられる可能性が高いからです。
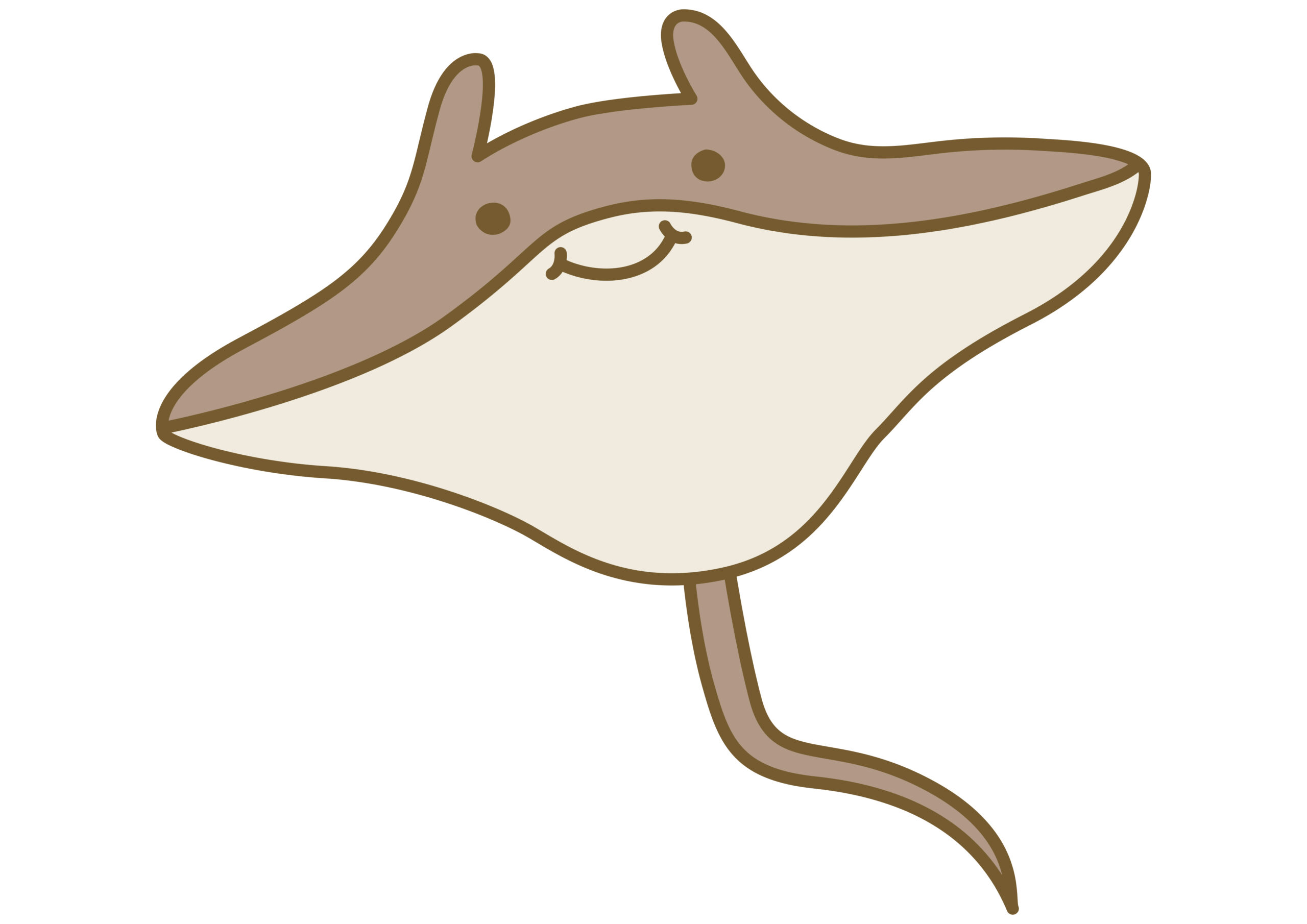
特に志望業界がないのであれば、土日祝日休みで対人サービスを行わない業界だと、長く勤められるでしょう。
小規模企業の求人が多い
ハローワークでの高卒求人を出している企業規模を見てみると、小規模の企業からのオファーが多いことがわかります。
| 規模別 | 令和4年(人) |
|---|---|
| 29人以下 | 127,244 |
| 30~99人 | 123,170 |
| 100~299人 | 78,055 |
| 300~499人 | 21,806 |
| 500~999人 | 19,095 |
| 1,000人以上 | 32,024 |
| 合計 | 401,394(人) |
小規模企業からの求人が多く、福利厚生が手厚いとされる大企業からのオファーは少ない傾向です。
規模の小さな企業だからといって、福利厚生が充実していないとは断言できません。しかし、従業員数の多い企業の方がさまざまなフォロー体制が整っているため福利厚生は充実しています。
例を挙げると、配偶者が転勤になった場合に「休職」制度を活用できる可能性が高く、家庭の事情に左右されずに在籍し続けられたりするのです。
一方で、人手の少ない小規模企業だと、アットホームな人間関係を築けたりすぐに責任のある仕事を任せてもらえたりなどの大規模企業では得られないメリットがあります。
会社で認められて濃い人間関係を築けば、妊娠・出産で職場を離れる機会があっても復職しやすいでしょう。
事業所規模別就職後3年以内の離職率
就活するにあたり業界の絞り込みも大事ですが、長く勤めるなら事業所の規模の大きさも重要です。
高卒・大卒に限らず、事業規模の大きさに伴い離職率は低下します。
| 事業所規模 | 高卒 離職率 | 大卒 離職率 |
|---|---|---|
| 5人未満 | 61.9% | 56.3% |
| 5~29人 | 52.8% | 49.4% |
| 30~99人 | 44.1% | 39.1% |
| 100~499人 | 35.9% | 31.8% |
| 500~999人 | 30.0% | 28.9% |
| 1,000人以上 | 25.6% | 24.7% |
事業所の規模が小さければ新卒で就業する人数も少なくなるため、辞職したときの割合も大きくなることに注意が必要です。
ただ、事業規模の大きい会社であれば、配属された部署が合わなくても異動できたり休職できたりと、とれる選択肢の数が多いです。
そのため、離職率低下に繋がっているとも見ることができます。
高卒女子が長く安定した会社員生活を送るには?
高卒女性が長く安定した会社員生活を送るには、以下のポイントに気を付けましょう。
- 安定した企業か公務員を狙う
- 不本意な企業に内定しても手を抜かない
詳しく見ていきましょう。
安定した企業か公務員を狙う
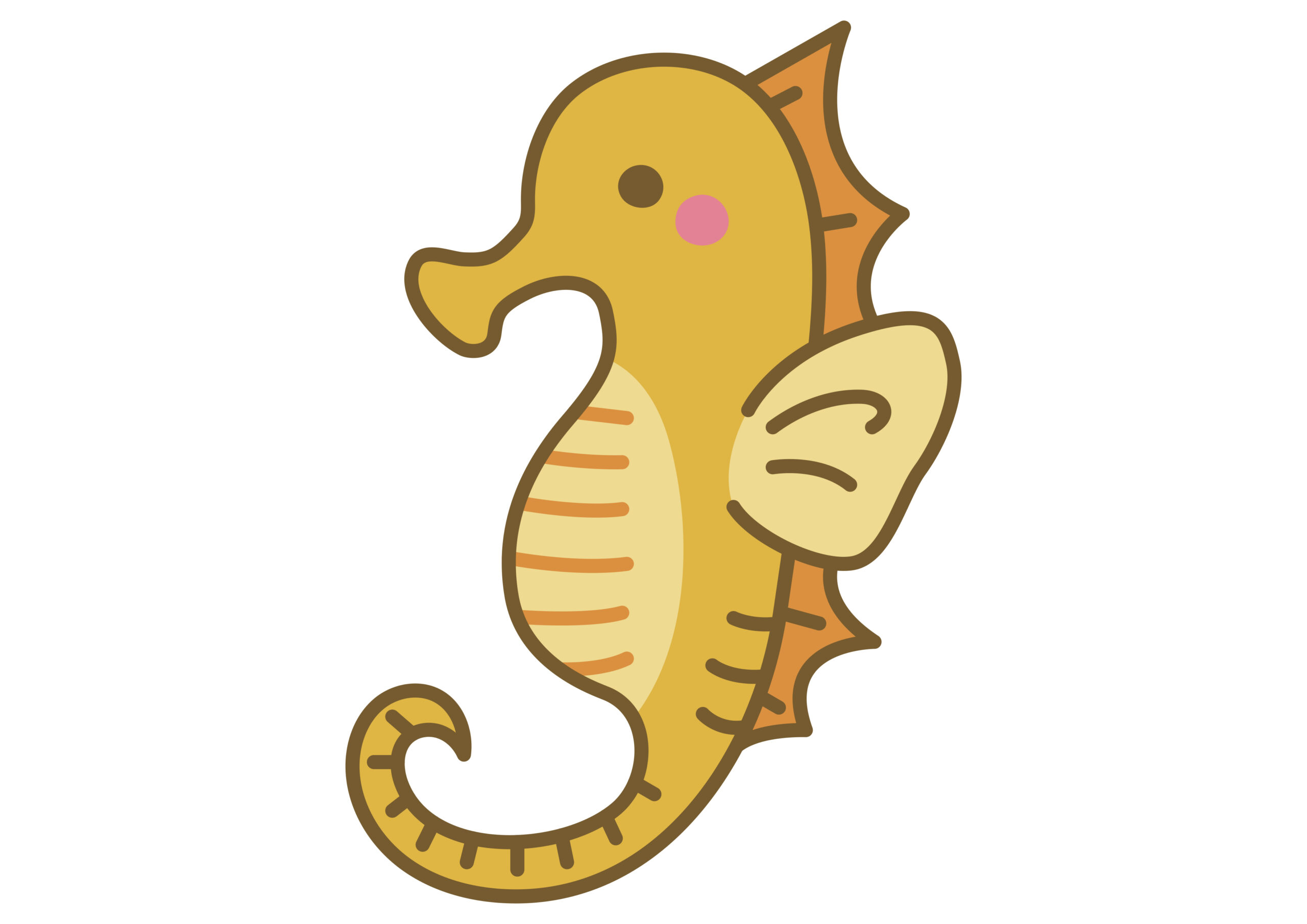
高卒女子が長く働き続けるなら、安定した企業か公務員を第一志望にして就職活動をしましょう。
安定した企業とは、大手企業や大手企業の子会社などを指します。ここで注意すべき点は、名前を知らない企業だからといってエントリーしないケースです。
BtoBといって企業相手に商売をしている会社だと、世間に名前は知られていなくても安定した業績で長く働けます。
民間企業へ就職活動をするときは、会社規模や親会社の有無などしっかり調べることが大切です。
公務員を第一志望にする場合、学校の定期考査で点数を取れるようにしましょう。高卒女子にとって公務員という職は非常に人気のある職種です。
産休育休をとってもちゃんと戻ってこれる環境が整っており、長く働き続けるにはまさにうってつけです。まずは、公務員試験にパスできるような学力を身に付けましょう。
不本意な企業に内定しても手を抜かない
不本意な企業に就職することになっても、仕事の手を抜くのは控えましょう。
就職率が高いからといって、全員が希望する企業に就職できるとは限りません。強く希望していない企業からしか内定が出なかった場合も大いにあり得ます。
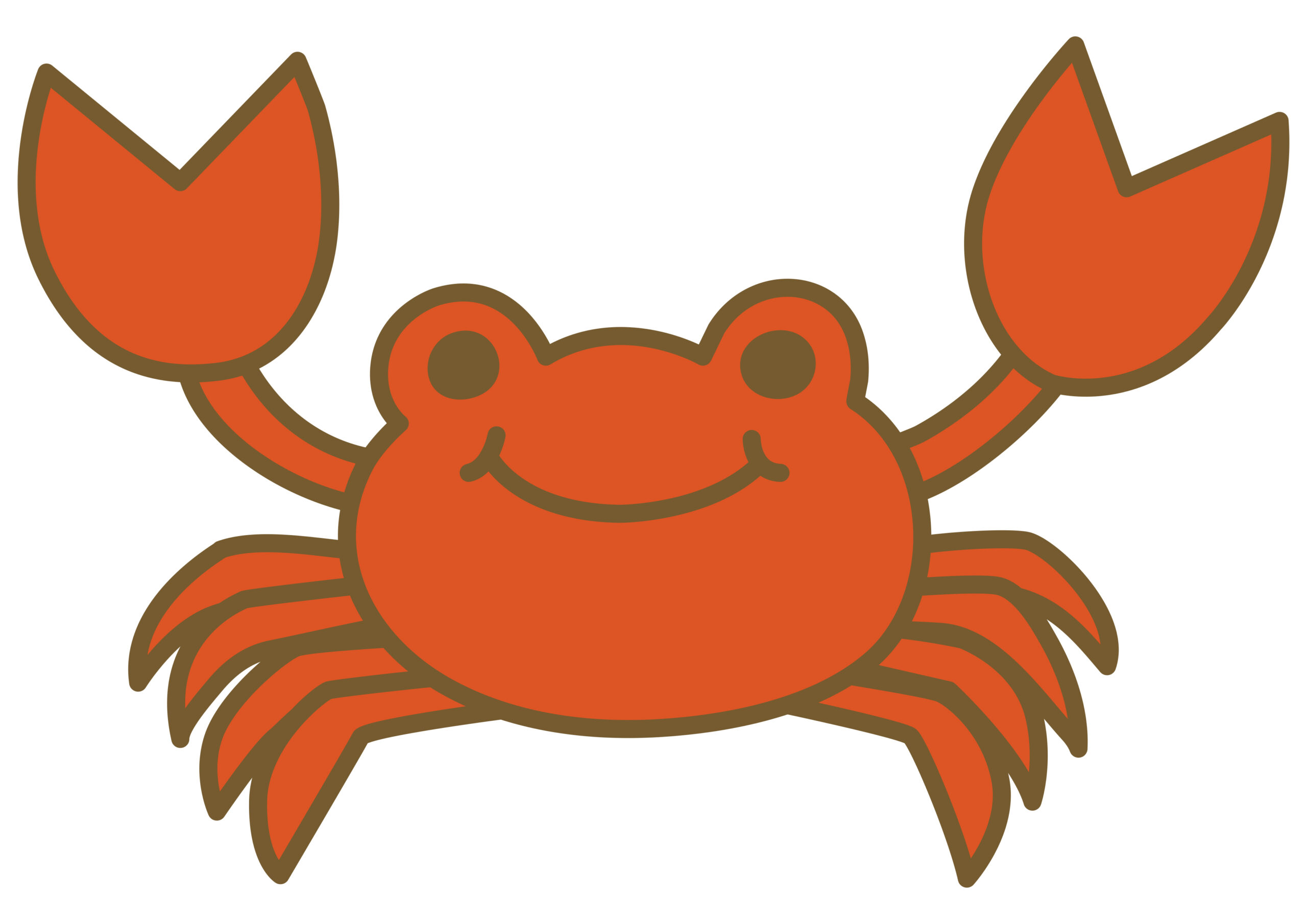
不本意な企業に内定したからといって、すぐに転職や退職を考えるのは早計です。
なぜなら、以下のように長く勤めるメリットが大きいからです。
- 社会的信用が上がる
- その職種の専門的知識が増える
- 濃い人間関係を築ける
不本意なまま仕事を楽しめない場合は、以下の点を意識しながら仕事を続けましょう。
- 転職を意識した仕事をする
- 資格取得を頑張る
”転職を意識した仕事をする”とは、職務経歴書や面接で話せるエピソードを作るということです。
事務仕事なら「エクセルに手を加えて業務効率改善に役立った」話や、接客業なら「積極的にお客様と関わって満足度を高めつつ売上向上させた」といった具体的なエピソードを語れるようにしましょう。
また、簿記やその職に関わる資格を取得するのも転職に効果的です。
「こんな会社に勤めるはずじゃなかった」といった、その瞬間の感情ではなく、長期的な視点を持って立ち回りましょう。
高卒女子におすすめの資格
転職を視野に入れているなら資格の取得に動きましょう。転職を考えていなくても資格を取得すれば、在籍している会社から手当がつくかもしれません。
高卒女子におすすめの資格は以下の通りです。予備校のリンクを貼ったので気になる資格があれば確認しましょう。
上記の資格は企業から求められており、転職時に評価されやすいです。行政書士なら資格取得すれば独立することも可能です。
人と触れ合うのが好きなら以下の資格をおすすめします。
介護福祉士は実務経験が4年あれば短期養成学校に通えるため、高卒者でも取得できる国家資格です。
資格を取得すれば未経験の業界でも転職しやすくなります。仕事をしながらの勉強は大変ですが取得する価値はあるのでチャレンジしましょう!
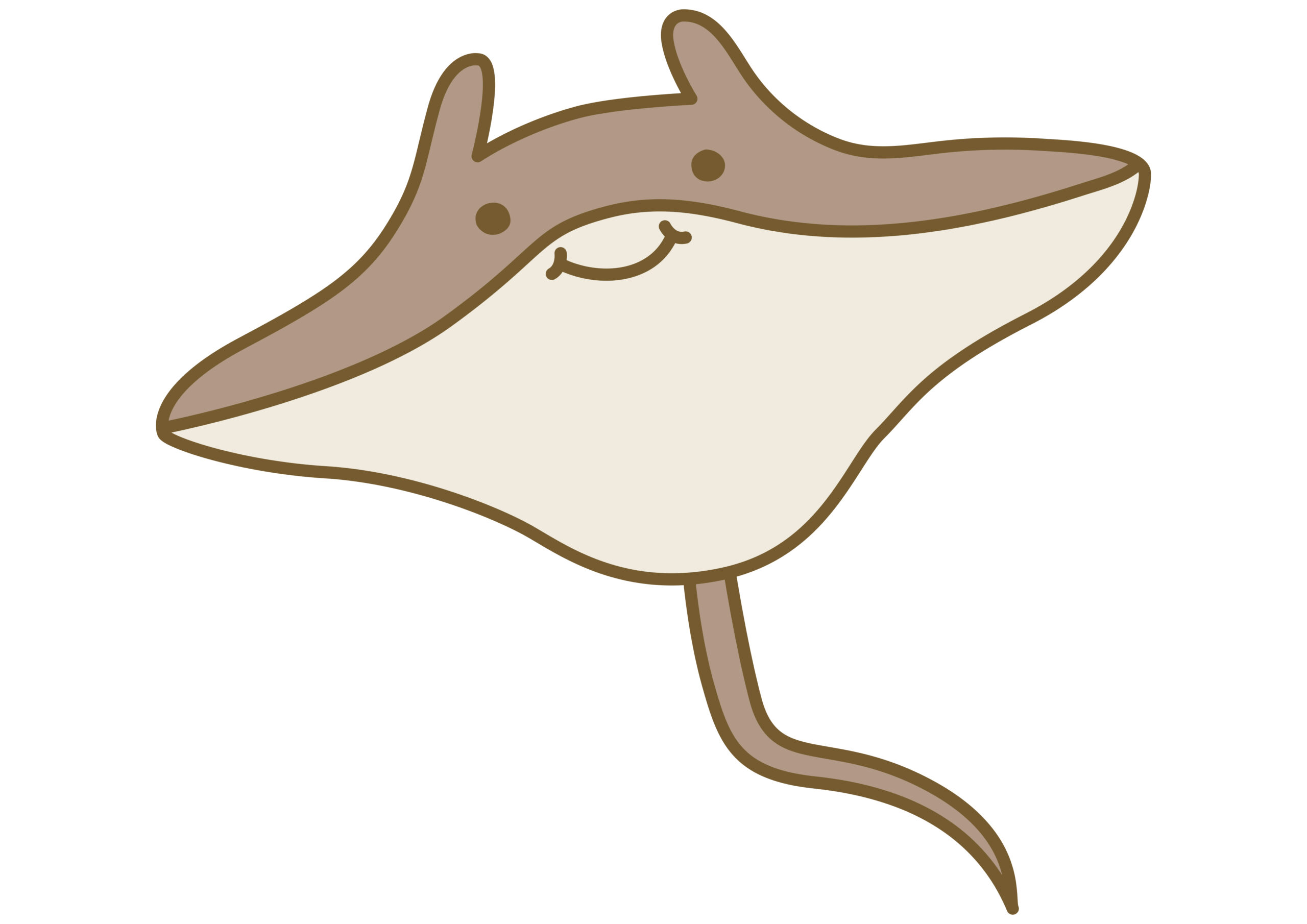
自分は就職したけど周りは学生…という状況だと、周りに流されて平日でもオールや飲み会で遊び倒してしまうかもしれません。
しかし、夜に自分の時間をとれる時期は意外と短いです。同棲や結婚すれば、夜に自分磨き(勉強)をする時間は取れなくなるでしょう。
自分の将来を考えるなら、勉強に集中する期間を作って資格取得に動くことをおすすめします。
大学に進学したほうが選択肢は増える
勉強が嫌だから高卒女子で就職しようと考えているなら、高卒で就職した場合の生涯賃金や働きやすさを確認したうえで就活を始めましょう。
「電車が好きで交通系の企業に就職したい!」や「公務員試験で安定した生活を一刻も早く手に入れたい」、「農業や伝統工芸で生計を立てたい」といった確固たる信念がないのであれば、大学に進学したほうが自分に有利な選択肢を手に入れられます。
もし、高卒で就職するなら安定した公務員や大企業への就職を狙うべきです。公務員や大企業、大企業傘下の企業であれば、福利厚生がしっかりしているため、長く勤めやすい環境で仕事できます。
仮に第一希望でない企業に就職することになっても諦める必要はありません。実際に働いてみると、意外と面白いと感じるケースは多いです。また、仕事内容に魅力を感じなくても人間関係が良好であれば仕事の満足度は高まります。
すでに高校を卒業した人で「今の職場から逃げ出したい!」と考えているなら、年収アップできるような環境を整えてから行動に移しましょう。
人生は高校を卒業してからの方が長いです。
自分の今後の人生を大きく左右する高校卒業後の進路は親との話し合いも含め、慎重に決めましょう!
大卒と高卒の賃金格差について詳しく切り込んだ記事はこちらです!!