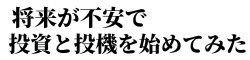投資ブログらしく、どのくらい資産が増えたのか報告します。筆者は2020年から投資を開始しています。
ビビりなので最初は少額から徐々に投資額を増やしていました。そのため、2023年上半期は投資額の増加と好調な市況により、一気に資産が爆増しました。
遅ればせながら、30代半ばで2020年から本格的に投資に興味を持って開始した筆者ですが、しっかり資産を増やせています。
この記事が、給料が低くて資産形成できていない30代半ばの人にとって、投資に踏み出す大きな一歩となることを期待しています。
Contents
投資開始から現在までの評価額推移
投資開始から現在までの評価額推移をグラフにしました。
グラフの波がガタガタな時期と平らな時期がある理由は、思いついたタイミングで入金&スプレッドシートに金額を入れていたためです。
そのため、年ごとに評価額の増え方が全然違います。
2020年から本格的に投資を開始し、2021年は一般NISAの枠を使い切るほど投資しましたが、評価額は微増です。2022年は一般NISAの枠を使い切ることができませんでした。
2023年は枠を使い切るために毎月の投資額を増やしています。
直近のグラフを見てみると、株式市場の好調さと自身の投資額の増加が相まって、ここ最近は一気に資産が増えていますね!
貯金とは違い今後元本割れの可能性はあるものの、ここまで資産が増えるとけっこう嬉しいものです。
筆者の基本投資スタイルはオルカン
筆者のメイン投資スタイルはオルカンです!
オルカンをメインに投資すると決めるまで色々な商品、個別株に手を出したため、口座内はバラエティーに富んでいますけどね。
オルカン一本にするまではS&P500に投資したり、米国や日本の個別株に手を出したりしていました。
投資初心者にとってオルカンが良いと言われている理由は、こちらの記事で詳しく解説しています。
最も損しないスタイルは株50:債権50
ちなみに、長い人生で最も損をしないスタイルは株50:債権50と言われています。
我々の年金を運用している機関GPIFは株50:債権50で目標利回りをほぼ下回ることなく安定した成績を出しています。
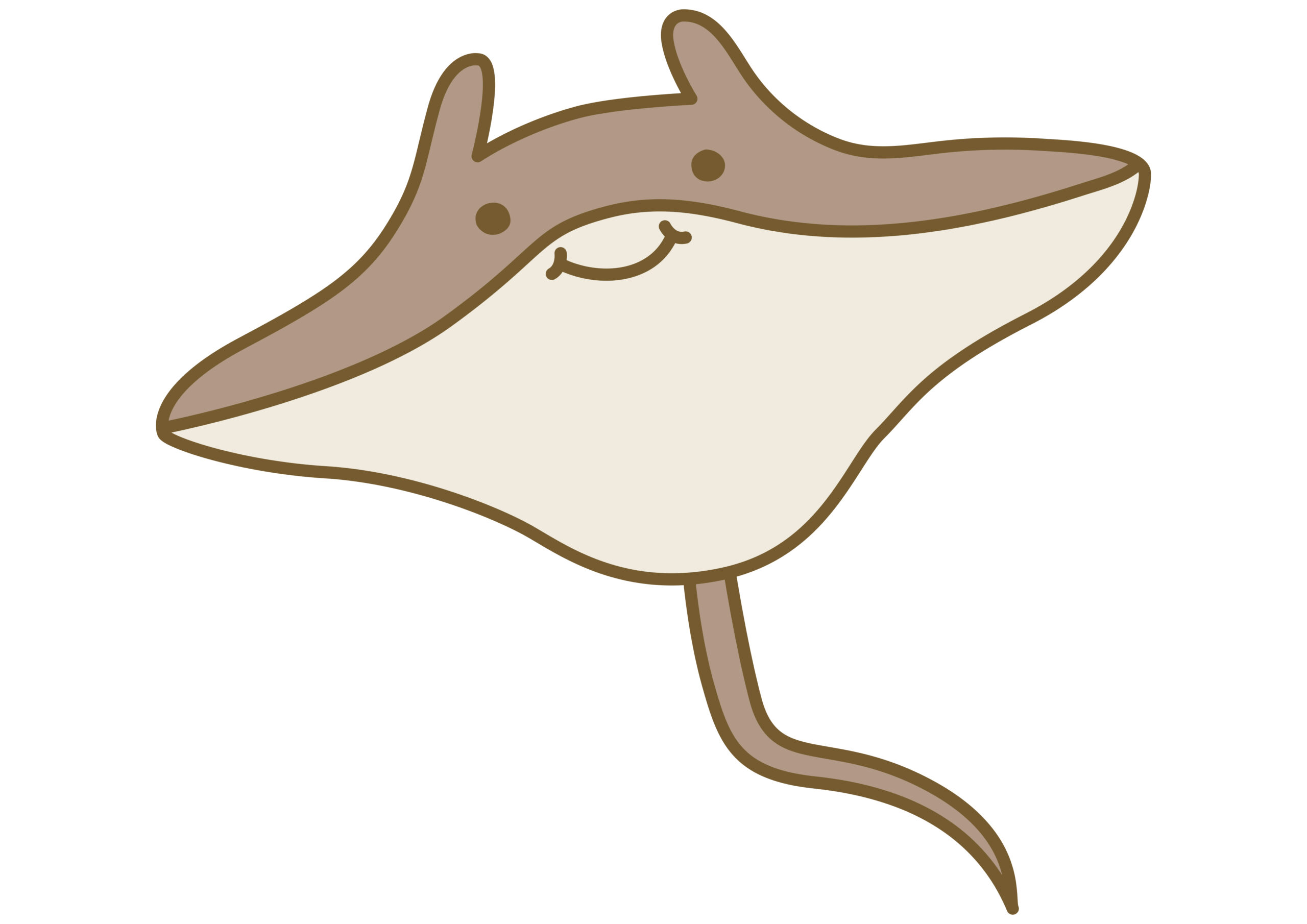
ちなみに、損する可能性が低いなら、大勝ちする可能性も低い。ということは頭の片隅に入れておいてください。
比較的評価額が乱高下しにくいオルカンですが、全世界の株式市場に連動するため、投資した額よりも低い評価額がつく(元本割れ)時期はあるでしょう。
性格的に元本割れする時期を受け入れ難いタイプなら、GPIFの投資スタイルを真似てみるのもいいかもしれません。
オルカンのパフォーマンス
オルカンへの投資は2022年1月から開始しました。オルカンのみのパフォーマンスは以下のグラフです。
2023年は上り調子ですが、それまでは含み損と含み益を行き来しています。2023年4月から投資額よりも評価額を上回り始めていますが、それまではほぼ投資額≒評価額でした。
今のところ、筆者の損益率は約14.5%です。
今後どうなるか分かりませんが、オルカンの評価額は個別株のような乱高下がないため安心して見ていられます。
「大きく儲かるかも…!」といった刺激は得られませんが、長期的な資産形成を行うなら安心です。
とはいえ、債権を組み込んでいるGPIFよりは乱高下していますけどね。
個別株
個別株は日本株と米国株に投資しています。
最も良い成績を叩きだしているのは、訳も分からず購入した米国株のNVDAです。まぁこれは運が良かったのでしょう。今は円安ですし高値で推移しているため、追加購入せずに放置しています。他の銘柄も持ってはいますがごく少数で、一番ボリュームの大きい銘柄はNVDAです。
日本株は、米国株と比べて色々な種類の会社の株を持っています。もちろん含み益を出している銘柄もありますが、含み損を抱えている銘柄もあります…。
ちなみに、個別株まで事細かに言及するとまとまりがなくなるので、詳細な運用報告はしません。米国・日本どちらもトータルで見れば含み益が出ている状態です。
30代後半でも投資すれば資産形成できる
30代後半でも毎月の投資額が少なくても、続けていれば資産形成できます。
筆者の場合、毎月捻出できる金額は限られていますが、貯金を崩して投資に充てています。
Twitterを見ていると、新卒からガンガン投資している若者が多いですよね。しかも収入が多いせいか資産額も雪だるま式に増えていく様子を見ていると、なぜか損した気分になります。
しかし、全く投資をしないよりも少しでも株式市場にお金を投入した方が資産形成しやすいのは事実です。
年を重ねてしまったのはどうすることもできないですが、少しでも明るい未来のために投資して老後に備えましょう。