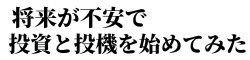「民法の勉強の仕方が分からない」と勉強開始したものの、圧倒的な範囲の広さで怖気づいていませんか?筆者は行政書士試験の受験を決めたことを後悔しました。
しかし、計画的な学習と演習で高卒&独学でも合格できたので、方法さえ間違えなければ合格できます。
今回は、民法の特徴と配点、科目ごとの勉強法について紹介します。本試験でとった点数も公開しているので参考にしてください。
Contents
民法の問題数・配点
民法の問題数と配点を以下の表で確認しましょう。
| 問題形式 | 問題数 | 配点 |
| 五肢択一式 | 9(1題4点) | 36 |
| 記述式 | 2(1題20点) | 40 |
行政書士試験における民法の割合は、76/300(点)と約25%です。行政法に続いて配点の大きい科目のため、得点源にしなくてはなりません。
民法の場合、記述が合否を左右します。2題で40点と大きな配点のため、記述対策が必要です。
高卒独学者の民法の得点について
行政書士試験の配点と筆者の本試験での点数を以下の図にまとめたので、確認しましょう。
実のところ、民法で点数を稼げていません。正答率は五肢択一式で6.5割ほどです。7~7.5割を目指したのですが、実現しませんでした。
2022年の試験では簡単な問題と難易度の高い問題の落差に焦ってしまい、手が震えたのを覚えています。普段だったら解けていた問題も焦りで間違えてしまったところもありました。
記述に至っては、4割しか得点できていません。当初の作戦では行政法の記述で20点を狙って、民法は1題正解の20点が取れればOKと考えていました。
実際は部分点で稼いだようです。とはいえ、行政法を含めた記述の点数は許容範囲内なので良しとしましょう。
行政書士試験で合格を目指すなら、民法の五肢択一式は6.5割以上、記述は14点以上がボーダーラインです。
民法の勉強でやるべきこと
範囲の広い民法の勉強でやるべきことは決まっています。
民法の勉強でやるべきポイントは、以下の3つです。
- 演習をこなす
- 問題文を図にする癖をつける
- 解きながら条文を覚える
民法の力を伸ばすには、とにかく実践が重要です。
演習をこなす
テキストを読んだら、理解できていなくても演習しましょう。理解するまでテキストを読み込んでも数ヶ月経てば忘れるため、最初から単元をマスターしようとすると効率が悪いです。
テキストを読んでピンとこなくても、さっさと実戦問題に取り組むのが吉!
分からないなりに演習をこなすことである日突然、理解が深まるときがきます。
テキストを読んでも理解できず、問題を解いてもチンプンカンプンで困惑するかもしれません。しかし、そのステップを踏んだうえで解説を読むと一気に理解がすすむケースも多いです。
重要なポイントは、同じ問題集を何度も繰り返すこと。
問われている論点を理解して条件反射で条文がでてくるまでやり込むと、民法が身に付きます。
問題を解く勘どころを育成するためにも、納得できるまでテキストを読むのではなく演習で理解を深めましょう。
民法の学習で絶対にゲットすべき問題集はこちら。
問題文を図にする癖をつける
問題文に出てきた状況を図に置き換える癖をつけましょう。民法の問題文は長くて複雑です。
読解力だけで理解しようとすると混乱や誤読する可能性が高いため、図に書き出して内容を整理することを心がけてください。
法律に関する文章は独特なため、図に書き出すだけでも読解力が求められます。1文ごとに「誰が何をどうしたのか」を把握しながら図に書く訓練が必要です。
人物関係を書き出すと、似たような条文である「即時取得」や「時効取得」どれを主張すべきか検討しやすいです。
また、それぞれの主張にあたって必要な要件も当てはめて考えやすくなります。
民法で正確な回答を導き出すために、問題文を図で表せるようにしましょう。
解きながら条文を覚える
問題を解きながら条文を覚えましょう。条文のみを素読して暗記する方法は非効率です。
特に、時間のない社会人受験生にとって効率的な暗記が求められます。
また、解きながら条文を覚えれば六法は必要ありません。筆者の場合は、テキストに付属している簡易的な六法も民法の勉強で使わなかったです。
演習をこなしていくうちに、嫌でも重要条文は頭に叩き込まれます。なぜなら、解説に重要条文のフレーズが掲載されているからです。
問題を間違えたあとの復習が暗記タイムとなるため、同じ問題集を完璧にすることで特定の論点と重要条文がセットで身に付きます。
問題を解きながら条文を暗記して、民法を効率良く学習しましょう。
民法の科目ごとの特徴と勉強法
民法の科目ごとの特徴と勉強法を確認しましょう。
民法は科目ごとに内容が分断されているわけではなく、薄っすらと繋がりがあります。
そのため、よくわかっていなくても1周させてください。2周目の学習で「これか!」と気付くケースも多いです。
民法の科目は5つあります。
- 総則
- 物権
- 債権
- 親族
- 相続
特徴ごとに、意識すべきポイントが異なるため順番に見ていきましょう。
総則
民法総則とは、物権や債権などの財産法に通ずる大まかなルールのことです。
行政書士試験だと財産法が主に出題されるため、民法総則もよく出題されます。特に、”権利の主体・客体”や”意思表示”は複雑ながら頻出問題のため、丁寧に知識を整理しましょう。
ただ、民法総則は抽象的なため、受験生が苦労する科目でもあります。
とはいえ、物権や債権を勉強する前に総則で共通ルールを勉強するわけですから、チンプンカンプンで当然です。
総則を学習するときは完璧な理解をしていなくても次に進みましょう。物権や債権を学習したあとに総則に戻ると理解しやすいです。
民法総則は財産法の共通ルールとなるため、暗記すべき事項が多いです。
基本的にノートでまとめる作業はお勧めしませんが、問題集2.3周目で理解できない箇所を整理するために自分で内容をまとめる方法はおすすめです。
物権
財産法である物権は行政書士試験で問題として出されやすい科目です。なかでも、”所有権”や”担保物件”は頻出なため、しっかり学習しましょう。
物権は人物関係を図に書き出して、問題文の情報を整理すると解きやすくなります。
演習量がものを言う科目なため、ノートに綺麗にまとめる方法よりも問題を解きまくった方が実力がつくはずです。
債権
行政書士試験の民法のなかで最も重要な科目が債権です。債権は頻出科目であり、ひねりのある問題が出されるケースも見られます。
特に、”契約以外の債権発生原因”は超頻出問題です。
債権の問題は複雑なため、条文と判例の確認を丁寧に行いましょう。特定の条例を判例と一緒に覚えると理解しやすいです。
演習した分だけ実力になる科目ではあるものの、基礎ができていないと多くの問題を解いても実力になりません。
まずは、基本問題集やスー過去を完璧にしましょう。
親族
家族法である親族は、比較的出題頻度の低い科目です。例年だと、だいたい1問程度の出題となります。
ただ、家族法は身近な法令のためイメージしやすく、得点源にしやすい科目です。時間がないからといって、捨てないようにしましょう。
軽くでいいので、テキストを読んだらすぐに基本問題集やスー過去に取り組みましょう。
時間のない人はテキストを読まなくても大丈夫です。
筆者はテキストを読まずに最初から基本問題集とスー過去に取り組みました。テキストは、勉強の休憩時間や気分転換、本格的に取り掛かるアイドリングとして読んでいましたよ!
相続
家族法である相続は比較的出題頻度の低い科目で、親族も含めて例年で1問程度の出題です。
相続も親族と同様に身近な法令のため、イメージしやすく得点源になる科目と言えるでしょう。
ただ、相続は若干複雑なため、最初にテキストを読んでから問題に取り組むことをおすすめします。
もしくは、問題を解いて、解説と一緒にテキストを読むといった使い方が効率的です。
何が問われているか意識しよう!
問題文で何が問われているのか意識して問題を解きましょう。
民法が難しいと言われる要因の1つに「問題で何を問われているかわからない」があります。同じ人物関係でも、立場が変われば適用できる法や要件が変わります。
また、似た状況で適用可能な法が複数あり、要件次第で選択肢が変わる問題文は少なくありません。
民法は国語力も試される問題が多いです。
民法の記述対策
民法の記述はトータルで40点と配点の大きい問題のため、十分な対策をしましょう。
記述対策で重要なポイントは3つあります。
- 記述問題を解くときの心構え
- 5W1Hを明確に読む・書く
- 適用条件・除外を意識
上記のポイントは、民法の記述問題を得点源にするために必要な知識です。
記述問題を解くときの心構え
記述問題を解くときの心構えは、問題文に忠実な回答を作ることです。
行政書士の記述問題だと、あらかじめ問題文に記述で書いて欲しい内容が示されています。出題者が求める内容を過不足なく記述できれば、20点満点が可能です。
そのためには、民法の重要条文と要件定義の正確な知識が求められます。
つまり、民法の記述は五肢択一式を完璧にしないと得点できません。逆を言えば、記述の学習をすることで五肢択一式の得点アップにつながります。
民法の問題をガシガシ解くフェーズに入ったと同時に、記述対策の問題集に取り組みましょう。
同時並行で演習することで適用可能な法と要件がセットで覚えられます。
5W1Hを正確に読む・書く
記述問題で得点するために、5W1Hを正確に読んだうえで書く必要があります。
5W1Hとは、以下の英語の頭文字をとった呼び名です。
- When:いつ
- Where:どこで
- Who:だれが
- What:何を
- Why:なぜ
- How:どのように
民法の記述問題は一見複雑な事象が絡み合っているように思えますが、5W1Hを整理するとシンプルな問題に変化します。
問題文を正確に読んで情報の取捨選択が求められるため、条文や要件の暗記だけでは太刀打ちできません。
5W1Hを意識しながら記述問題に取り組みましょう。
適用条件・除外を意識
適用条件と適用除外を意識すると、グッと正答率が上がります。
民法は似たような法律が多く存在し、主張できるかは適用条件や適用除外に該当の有無で変わります。
また、インプットできていてもアウトプット(記述)できるとは限りません。特定の条文を見たら、すぐに適用条件・除外が頭に思い浮かぶようにしましょう。
そのため、適用条件や適用除外といった要件定義の把握が重要です。
独学での民法勉強まとめ
民法を独学で勉強するなら、わからなくても立ち止まらずに前に進むことが重要です。
どの科目も薄っすらつながりがあるため、1回で理解できなくても他の科目を学習したあとならスルスルと頭に入ってくるなんてことは珍しくありません。
行政書士試験の民法は、わからなくても諦めずに学習し続けた人が勝者となる試験です。
「わからない」「できない」「焦る」といったネガティブな感情は一切無視して、淡々と取り組みましょう。
理解できるようになる日は絶対にきます!!そして、その日は突然やってきます!
また、学習するうちに膨大な試験範囲に不安になるかもしれません。学習進度が遅くても勉強していくうちに、だんだんペースアップできるようになります!安心してください。
日の目を見れるよう今は種まきの時期だと割り切って勉強する心構えが大切です。
独学だとペースが掴めないなら予備校に通う選択肢も
「仕事や家事育児で忙しくて、独学だとペースが掴めない…」と困っているなら、予備校や通信教育に通うことを検討しましょう。
行政書士試験は年に一度の試験のため、不合格になるとリベンジ合格まで1年を要します。
時間を確保できずに何度も受験するくらいなら、ペースメーカー代わりに予備校に課金した方がコスパの良いパターンもあり得ます。
最も回避すべきは何度も受験を繰り返すことです。受験すればするほど費用も時間もかかるため、一発合格を目指すつもりで勉強しましょう。
一発合格するために独学だと不安なら予備校に通って、効率良く知識を吸収するのもひとつの方法です。
おすすめの予備校を紹介します!
まずは、LECリーガルマインドです。きめ細やかなフォローを求める人に向いています。
LECは大手の資格取得支援予備校です。行政書士試験で有名な横溝講師が在籍しており、商法などのマイナー科目までしっかりカバーしています。
そのため、講師の指示通りカリキュラムをこなしていけば合格圏内に実力を底上げできます。
横溝講師の雰囲気や講座の内容を知りたい方はYouTubeで確認しましょう!
横溝講師のブログも人気です。独学者でも参考になるポイントが多いので、一度は目を通しておくと勉強のヒントを得られます。
筆者も勉強に行き詰ったときは横溝講師のブログを読んでいました。
↓LECリーガルマインドの公式ホームページは下のバナーから

続いて、アガルートの紹介です。合格特典が豪華のため一発合格を目指す人におすすめ。
アガルートの特徴は、オンライン講座のため場所・時間問わず無駄なく受講できることです。
オンラインに特化したカリキュラムのため、講座の選び方や受講講座相談などサポート体制が充実しています。
アガルートだと豊村講師が有名です。豊村講師の授業はYouTubeから確認できますよ!
アガルートは一発合格すると、お祝い金5万円分のアマゾンギフト券か受講料全額返金という、大盤振る舞いな合格特典が用意されています。
↓アガルートの公式ホームページは下のバナーから

オンライン授業がスタンダードになった現在、比較的リーズナブルな予備校も存在します。独学で苦戦している人は自分にあった予備校の資料を取り寄せて検討してみてください。